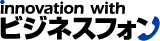テレワークや外回りなど、オフィス以外で働くスタイルが当たり前となった今、会社の電話をどこででも受けられる仕組みが求められています。
そんなニーズに応えるのが「FMC(Fixed-Mobile Convergence)」です。
固定電話と携帯電話の通信を融合させるFMCは、外出中でもスマートフォンで会社の電話を受けることができ、内線通話として運用することが可能になります。この記事では、FMCの仕組みや他サービスとの違い、導入によるメリット・デメリットを解説します。
FMCとは?

FMC(Fixed-Mobile Convergence)とは、従来のPBXを利用した、固定回線と携帯回線を融合させた通信サービスのことです。
携帯電話やスマートフォンを社内内線として活用でき、たとえ外出中でも、まるでオフィスにいるかのように会社番号で発着信が可能になります。
現在、多くの通信キャリアがFMCサービスを提供しており、柔軟な働き方を支えるインフラとして注目されています。
FMCには主に2つの形態がありますので簡単にご紹介します。
キャリアFMC
NTTドコモやソフトバンクなどの通信事業者が提供するモバイル回線で、キャリアの通信網と連携した形で固定・携帯を一体化させます。
アプリFMC
スマートフォンに専用アプリを導入することで、社用携帯に会社の固定番号も割り当てられる形態です。スマホ1台で「会社電話」と「個人電話」を一本化できます。
FMCのメリット

では、なぜオフィス以外で働くスタイルにとって、今FMCが求められているのでしょうか。
メリットについてポイントを解説していきます。
外出先でも「会社の電話」が取れる
スマートフォンが内線化されることで、出張や外出時でも会社番号での発着信が可能に。テレワークや出張先、営業活動中でも電話対応の抜け漏れを防げます。
通信コストの削減
内線通話は無料となるため、通話料金が大幅に節約できます。キャリアを一本化することで管理コストも抑えられます。
既存端末が使えることも
FMCは既存のスマートフォンをそのまま利用可能な場合もあります。
機会損失を防ぐ
いつでもどこでも着信に対応できるため、担当不在による取り次ぎの手間や不在着信による機会損失を防ぐことができます。
柔軟な働き方を後押し
自宅・出先・コワーキングスペースなど、場所に縛られず仕事ができる環境を整えるうえで、FMCは有効な手段となります。
FMCのデメリット

FMCの利便性からは一見デメリットがないように見て取れますが、契約周りなどいくつか気になる点もあります。
キャリアの統一が必要
固定電話とモバイル端末を一つのキャリアにまとめる必要があるため、契約変更や、異なったキャリアを利用している場合には違約金が発生する可能性があります。そのためBYOD(私用端末の業務利用)との相性が良いとは言えません。
外線発信時は携帯番号が表示される
FMCアプリから外線を発信すると、相手に携帯番号が通知される場合があります。知らない番号と認識され、電話に出てもらえないことや、個人携帯として登録され営業時間外に電話がかかってきてしまうリスクもあります。
高額な機器や保守費用がかかる
FMCの導入には、PBXとの連携が前提となるケースが多く、高額な初期費用や継続的な保守費用が発生することがあります。
社内に専用機器を設置するためのスペース確保、老朽化対応、保守契約など、中長期的に見てもランニングコストがかさむ傾向にあります。
コスト削減効果が限定的な場合も
外線通話が多い業務形態だと、内線通話の恩恵をあまり受けられず、コスト削減にはつながらないことも。
クラウドPBXとの違い

クラウドPBXは、PBX機能をクラウド上で提供し、複数キャリアにも対応するサービスです。
FMCではキャリアを統一する必要がありますが、クラウドPBXではその必要がありません。また、外線・内線問わずインターネット回線で管理できるのも特徴です。
FMCと比較すると、クラウドPBXは通話管理や複数拠点での運用に優れています。
目的と仕組み
FMCは、固定電話と携帯電話の通信を統合し、スマートフォンを会社の内線電話として活用する仕組みです。特に、外出先でも内線通話ができるようにすることを目的としています。
一方、クラウドPBXは、従来オフィスに設置していたPBX(電話交換機)をクラウド上に置くことで、場所や端末に縛られずに電話業務全体を一元管理できるシステムです。内線だけでなく外線通話も、インターネットを通じてどこからでも対応できる点が特長です。
外出先での電話対応
FMCでは、スマートフォンを内線端末として使えるため、外出中でもオフィスにいるような感覚で内線通話が可能になります。ただし、外線を発信すると携帯番号が通知される場合があり、会社番号としての信頼性にはやや欠ける場面もあります。
これに対してクラウドPBXでは、スマホにアプリを入れるだけで会社の代表番号での発着信が可能です。つまり、外出中でも「会社の電話番号での外線発信・着信」がそのままでき、顧客に与える信頼感も維持できます。
契約の柔軟性とコスト
FMCは、キャリアとの契約に加え、PBXの高額導入費用や保守費用が発生します。
クラウドPBXは月額課金制が主流で、初期費用が抑えられるうえ、契約期間の縛りがないサービスもあります。必要な分だけ内線・外線を追加・削減できる柔軟性も、スモールスタートや段階的な導入に向いています。
また、FMCは物理的なPBXに結び付いているため、拠点追加や人員増加に対応しようとすると、都度工事やシステム設定変更が必要になります。拠点や人員が増えるほど、柔軟な運用が難しくなります。
それに対しクラウドPBXでは、急な増員でもオンライン上で追加・削除・設定変更などを簡単に行えるため、迅速な対応が可能です。
災害や緊急時の対応力(BCP)
FMCは、PBXなどの物理機器が社内にあるため、地震や水害などの災害時に設備が損傷すれば、電話機能そのものが停止するリスクがあります。
一方、クラウドPBXはサーバーがクラウド上にあるため、インターネットさえあれば通話が可能です。パンデミックや停電時などでも、社員のスマートフォンから会社用番号で通話ができ、BCP(事業継続計画)対策としても非常に有効です。
柔軟な電話業務を実現するなら「トビラフォン Cloud」
FMCはあくまで「通話の延長」を目的とした技術であり、電話業務全体の効率化や情報活用といった面では限界があります。
より高度な電話管理・業務効率化を目指すなら「クラウドPBX」の導入が効果的です。
トビラフォン Cloudは、スマートフォンにアプリを入れるだけで外出先でも内線・外線の発着信が可能なビジネスフォンサービスで、FMCでは実現できない機能が多数搭載されており、日々の電話業務をよりスマートかつ柔軟に変えてくれます。
ここからは、FMCにはないトビラフォン Cloudの機能についてご紹介します。
音声テキスト化機能で、通話内容を自動で記録・活用
トビラフォン Cloudには、通話内容をAIが自動で文字起こしする「音声テキスト化」機能が搭載されています。
これにより、「誰が」「どのような内容で」「どんな対応をしたか」が可視化され、メモを取る手間がなくなるだけでなく、会話の行き違いや言った言わないの防止、情報共有の迅速化にもつながります。
IVR(自動音声案内)で電話の振り分けを効率化
トビラフォン Cloudは、着信時に「○○の方は1番を押してください」といった自動音声案内(IVR)を設定可能です。
部署や問い合わせ内容に応じた振り分けができるため、オペレーターの負担を減らし、顧客を適切な対応先にスムーズに誘導できます。
好きな電話番号での発信・着信に対応
トビラフォン Cloudでは、ユーザーごとに希望の電話番号を設定可能です。
しかも、その番号での発着信がスマートフォンからでもできるため、たとえば東京の番号で大阪から電話をかけることも可能です。(東京に事務所があることが前提です)
電話業務の一元管理が可能
トビラフォン Cloudでは、通話履歴や顧客情報をクラウド上で一元管理し、キーワードで検索することが可能です。
顧客名、電話番号、対応履歴などをすぐに呼び出せるため、「前回いつ対応したか」「担当は誰か」といった確認作業がすぐに完結します。
今こそ電話業務の見直しを

外出先や在宅勤務中でも“会社の電話”をそのまま使えるFMCは、働き方改革を支える重要な手段の一つです。
ただし、より広範な電話業務の効率化や、拠点横断での通話管理にはクラウドPBXが適しています。
「トビラフォン Cloud」はFMCの弱点をカバーしつつ、より高機能なサービスで、あらゆる働き方に対応した柔軟な通話環境を提供します。
FMCを超えた、クラウド型ビジネスフォンをお探しなら、ぜひ「トビラフォン Cloud」をご検討ください。
トビラフォン Cloudの詳しい情報はこちら
https://tobilaphone.com/biz/cloud/